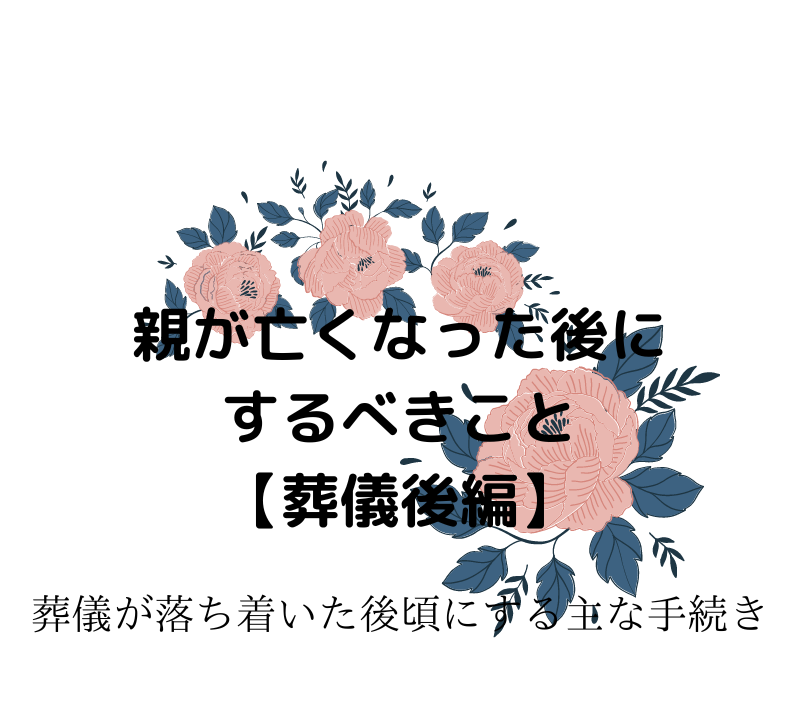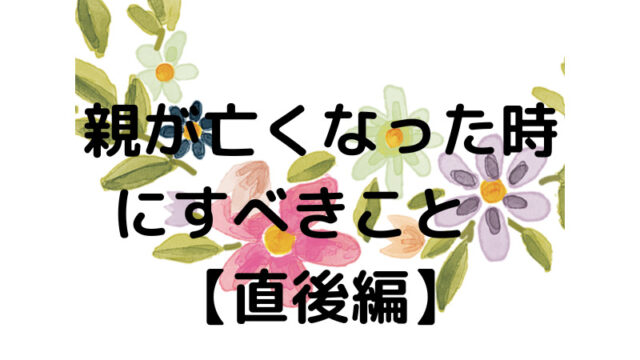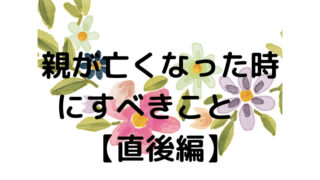親が亡くなった後にするべきこと【葬儀後編】
今回は、親が亡くなってから4~5日経過し、葬儀が終わって慌ただしさから落ち着いてきた頃、当面行う必要がある各種手続きについてまとめました。75歳以上の夫婦のみ世帯、年金収入のみ(少な目)、の夫が亡くなった場合を主な想定としています。
- 死亡診断書・死亡届、火葬許可証(埋葬許可証)・・・【直後編】を参照してください。
- 健康保険の手続き(故人)・・・国民健康保険の方、75歳以上で後期高齢者医療制度の対象となっている方は、在住の区市町村に死亡届を出すことで資格が喪失します。
- 健康保険の手続き(故人の家族)・・・葬儀を行った方(喪主)に一定の葬儀費が支給されます。申請には葬儀を行った方(喪主)の氏名が確認できる葬儀の領収書が必要です。
- 健康保険が組合健保、協会けんぽ、共済組合の場合・・・それぞれの規定に応じて、事業主を通して手続きを行う必要がありますので、各自で調べて対応してください。
- 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証を所持している場合は、返還を求められますので、何かの用事で役所に行くときに持っていきましょう。
- 年金は、役所に死亡届を出すことにより、年金を一時的に止めることになっていますが、別途、手続きが必要なことがあります。また故人の妻が遺族年金をもらえる可能性や、未支給年金の請求が可能な場合があります。年金の手続きは、故人が受け取っていた年金の種類などにより異なりますので、各自で年金の内容を全部調べて、確認して対応する必要があります。
- 年金の受給権者死亡届、遺族年金、未支給年金の手続きや、生命保険の受け取り、銀行預金の名義変更、相続関係手続では、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要な場合があります。ただし、死亡届を出してから一定の(概ね一週間前後)事務処理期間を経てから、亡くなったことが記載されますので留意してください。
- 区市町村によっては、上記③の他に、特定葬儀場の助成制度等が申請できる場合がありますので、チェックしてください。
- 世帯主変更・・・世帯員が故人の妻だけ、のように世帯主になる人が明白な場合は、届け出を出さなくても役所が自動的に処理してくれます。上記⑥、⑦の手続きの中では、故人の妻が世帯主になった後の住民票の提示等が必要な場合があります。
- 故人の所得税の確定申告・・・個人の年金受給が年間400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。故人が事業を行っていた場合、給与所得があった場合などは、相続人に義務が発生するか否か、よく確認する必要があります。